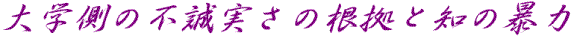
駒場寮廃寮問題も、廃寮反対闘争も、まもなく九年目を迎えようとしているし、新入生がこの冊子を手にする頃には、裁判の判決も出る直前である。国と大学が原告となって寮生(学生)を訴えている裁判であるから、東京地裁の三人の裁判官は余程の胆力と勇気と正義に忠実な人物でない限り、寮生側に不利な判決が予想される。寮生側に立って、学内寮の存続に力を貸そうとする教師(教授会メンバー)も少数なので、裁判官の心証形成上不利である。学生の意思は、昨年一二月の全学投票で四一一五票中の五七%の者が、一旦白紙に戻し、話し合いによる解決を求めているので、ハッキリとしている。あとは教授会メンバーが、教師が、話し合い解決に向かって最後の努力をするか否かにかかっている。 私は学内寮は一部でも残し、寮の建物は取り壊さず有効に使い(寮+他の機能)、周辺の樹木を守る立場に立つ。駒場再『開発』に反対の立場である。駒場キャンパスの一角に夜中でも明かりがともっている温かい生活空間が大学の中にあることがどれほど大事であるかなど、廃寮反対闘争に参加する過程で思い知らされ、考えてきた。私のこの問題に対する立場は、裁判所に出した二つの陳述書や、この二年間の入寮案内冊子に認めている。詳しくはそちらをご覧いただくとして、今は以下の二つのことを記させてもらおう。
一、不誠実さの根源はお金
最近、『モモ』という作品で知られるミヒャエル・エンデが晩年お金の支配に対して、それを克服する方法はないものか必死に考え続けていたことを知り、多大な感銘を受けた。お金は本来の交換手段に帰すべきであり、お金は老化しなければならない、また通貨は誰が発行してもよく、いくつもある方がよい(地域通貨など)ことを知った。近来にないうれしい啓発であり、啓蒙であった。
昨日、授業に関連して昔読んだマルクスの『経済学哲学手稿』(藤野渉訳、大月国民文庫)の第三手稿「貨幣」の件を繙いてみた。次の一節は有名な件であるが、久しぶりである。
「貨幣は、個人にたいしても、それ自身『本質』であると主張する社会的等々の絆にたいしても、この『転倒する』力として現れる。貨幣は誠実を不誠実に、愛を憎に、憎を愛に、徳を悪徳に、悪徳を徳に、下僕を主人に、主人を下僕に、愚鈍を分別に、分別を愚鈍に転化させる。
貨幣は、価値の現存し活動している概念として、すべての事物を混同し取りかえるのであるから、それはいっさいの事物の全般的な混同と取りかえ、つまり転倒された世界であり、すべての自然的および人間的な性質の混同と取りかえである。
勇敢を貨幣で買うことのできる者は、たとえ彼が臆病であっても、勇敢なのである。」
この件を読んでいて、駒場寮を強引に廃寮にもっていこうとする大学側の「不誠実さ」「悪徳」の本質がハッキリしてきた。それは当初から気づき、わかっていたことであるが、最終局面に至って、より鮮明になったという性格のものである。
駒場寮廃寮問題の最大の問題は二つある。一つは寮生や寮委員会に秘密裏に廃寮を教授会側、大学側が決定した「不誠実さ」約束違反にある(69年東大確認書、84年合意書違反)。この点を反省せず、その後何百回話し合いをもってもこの「不誠実さ」は解消されない。なぜなら大学側は廃寮の決定を撤回しないからである。
二つめは、『学内の』自治寮という文化(社会的共通資本)を『学外の』一大マンモス学生団地に変質して移してしまうことの是非である。学生の自治による寮を大学の厚生掛を大家さんとする学外のアパートに変えてしまう問題である。
個室志向の学生がふえ、相部屋の駒場寮の需要が最盛時の900名から300名台に落ちていたからといって、それを撤去して駒場7000名全体の福利厚生ゾーンとして再利用したいという大学側の言い分が正しいか否か、大学側が訴えているのは、この言い分であるが、ここにも空間を効率よく使う効率性の論理が全面に出ている。
新入生諸君にも、在学生や同僚(教員)や職員の皆さんにも指摘したいことは次のことである。
そもそもこの問題は、国有地の不効率利用をやめ、内需拡大を目指した当時の政府の政策に端を発している。旧三鷹寮のあった敷地は緑が豊かであった。東大が所有しているその国有地をもっと効率よく活用せよ、その計画を三年以内に提出せよ、提出なき場合は、国に没収する。この通達に屈して教養学部当局(学部長室)がひそかに当初1500の個室をもつ国際学生宿舎案を考え(三鷹市の条例に抵触するためか千五百は千に改められた)、文部省、大蔵省に脈あることを感得し、秘密裏に教授会、評議会で決定したのが、三鷹国際学生宿舎建設案であった。マンモス学生団地案であったので、駒場寮廃寮=吸収を前提にした案であった。
国有地の不効率利用の改善。内需拡大のために打ち出されたこの政策は、景気回復のためのものであったから、この政策の主人公はお金(貨幣)である。開発が大義名分であった。今思えば、三鷹地区の緑の保全のためにこのマンモス学生団地案も慎重に考えるべきであった。緑地が大幅に失われることになるからである。自然を残すか、GDP(GNP)をあげるか、環境保護かお金か。学内の敷地をめぐってであれば、議論は沸騰したであろうが、遠く隔たっている三鷹地区であった。学部長室(原田義也学部長)が教授会メンバーにも秘密裏に進めていた案なので、一回の教授会に電撃的に提案されては対応しきれなかった面はあるにしても、教養学部教授会の責任はまぬかれない。その責任は遅まきながら駒場寮廃寮決定を再考するところで一部とりもどすことはできるのである。
駒場寮廃寮を合理化する論理は、先にも述べたように駒場再開発(7000名のための福利厚生ゾーン建設)であり、土地の不効率利用是正である。効率性の論理には自然保護の視点はない。ただ単に付け足しの形で言及されるだけで、本当にそれを守ろうとする姿勢はない。そして開発すればお金が動く。公共投資で経済が潤うという論理である。
寮生(寮委員会)たちが廃寮決定を再考せよと再三要求しているにも拘わらず、大学側(永野三郎学部長特別補佐や浅野攝郎学部長)は社会に対する責任があって今さら変更はできないと言い続けているのであるが、社会的責任とは、お金をもらい(予算がつき)、すでにそれを使っているので元に戻せないというのが本質ではないか。不効率利用是正の声、内需拡大=開発主義に抗しきれなかったという言い分の本質は、お金の力に勝てなかったということではないか。
廃寮決定の経過や親元への手紙、指導教官による圧力、ガードマンの導入を見るとき、東大当局、とりわけ教養学部当局、廃寮やむなしとする駒場の教授会メンバーの側に「誠実さ」や「徳」はなく、犠牲者の寮生側にそれがあることは明白である。しかるに教養学部当局が配布する「学生の皆さんへ」文書や永野三郎氏の「創造的キャンパスライフをめざして」(『東京大学は変わる』所収)には反省ぶりは微塵もなく、逆に非常に美しい言葉で、「誠実さ」や「徳」の具現者のような自己主張をし、「不誠実」や「悪徳」は大学の廃寮決定にも従わない寮生側にあると描いている。
国や学生側に「不誠実」と「悪徳」があり寮生側に「誠実」と「徳」があるにも拘わらず、国や大学側がそれを『転倒して』主張している力は何か。マルクスの指摘によれば貨幣(お金)の力である。国有地の効率利用、開発の論理、つまりお金の論理である(自然保護の論理と正反対の)。
大学側(大学当局、教授会)の不誠実さ、あえていえば『きたなさ』(学生投票の批判を見よ)の本質は貨幣(お金)の不誠実さ、きたなさである。どんなに福利厚生だの、新しいキャンパスライフなどの美しい言葉を並べようと、作文をしようと、そしてそれで自分をごまかそうとしても、不誠実さ、きたなさは消えない。それに目をつむり、あとは大量のガードマンを雇って、自分たちは手を汚すことなく、大掃除してしまおう―駒場の教授会は総体としてこれをやろうとしていないのか。
「勇敢を貨幣で買うことのできる者は、たとえ彼が臆病であっても勇敢なのである。」
ガードマンを雇って廃寮を貫徹しようとすることほど卑怯な手はない。なぜ教授会は寮生たち、話し合いを求める学生たちを説得できないのか。言論で説得できず、物理力=暴力で事態を処理しようとするのは、言論の府、理性の府、真理の府の大学の自殺行為ではないのか。
二、大学当局による知の暴力
いま一つ、指摘したい。この一月『東京大学は変わる――教養教育のチャレンジ――』(東大出版会)という本が出版された。教養学部設立50周年記念出版と銘打ってあり、編者は新旧の学部長・評議員であるので、教養学部当局の出版物のようであるが、寮の明け渡しを求める判決が出る直前のこの出版は、大学当局にとって、極めてタイムリーであり、原告側の主張を学内外に知らせる役割を果たす。
教養教育の「技術革新」という章の末尾に収められた、駒場寮廃寮を根拠づける前記永野三郎氏の一文がそれである。この一文の質の低さを二つ指摘する。
一つは、キャンパスを機能的にいくつかのゾーンに分ける再開発計画が披露されているが、アカデミックゾーンと福利厚生ゾーンに分け、後者を東部地区にまとめてしまうという発想は、きわめて貧困な発想であり、世界的にも通用しない遅れたものであることをまず指摘したい。研究棟や教室の合間、合間に喫茶室や食堂が介在する方が便利でもあり、活き活きしたキャンパスになる。ヨーロッパの古い大学が街の中にあり、大学の中に街の一部があるような市民に開かれた大学は、一つの理想となっている。
都市の各地区を商業地区、住宅地区、文教地区など機能で分けるゾーニングに反対して、ジェーン・ジェイコブズは、都市の各地区は必ず二つあるいはそれ以上の働きをするようになっていなければならないという多様性の原則を、都市建設の四大原則の一つとしてあげている(宇沢弘文『ゆたかな国をつくる』岩波書店96頁)。この原則は生活者の感覚によく合う。この本で全国、全世界に披露された駒場再開発計画の思想は、見識と教養の低さを示して余りある。
廃寮推進派の永野氏たちが駒場の自然を守るためにいかに心をくだいて『いないか』は、「自然環境の保全と整備」の項がわずか七行しかなく、一読しても付け足しの感じしかしないことで立証されている。
この本につき、もう一つ指摘せざるをえない。執筆者たちの印税を犠牲にして駒場の教授会メンバー全員にプレゼントされたため、一部を読むことができたのであるが、蓮實重彦氏の短い一文であれ、山内昌之氏のながい「リベラル・アーツとしての教養教育」論(第二章)であれ、現在の三層構造からなる駒場の研究・教育体制はうまくいっているという自己紹介(自画自讃)があるだけで、重大な欠陥をもっているとか、重大な矛盾をはらんでいるという苦悩の筆致はさらさらない。この改革を推進してきた者の筆になるから必然かもしれないが、批判精神の欠如を覚える。彼らの考える教養教育の中身がどの程度のものかは、その文章自体からわかるが、効率主義や開発主義と対決する姿勢はどこにもない。駒場寮を廃寮にすることへの痛みや、その後の再開発で数百本の樹木を伐ることへの痛みはどこにも語られていない。駒場寮を過去の遺物として一掃の対象としか見なかった蓮實氏にそれを期待するのは元々無理ではあるが、しかし山内氏の能文が、今の駒場の知性を表すとしたら、悲しいし、恥ずかしいし、「巧言令色鮮(すくな)し仁」の典型というしかない。
今ここで言いたいことは、教養学部当局が経過はあるにしろ、今この時点でこのような本を世に出したことは、たとえその知が教養学部当局や執行部の知の表明であるとしても、知の暴力である側面をもつことを指摘したい。権力をもっているとはこのようなことなのか。
寮生や支援するOBたちの訴えは手作りの冊子や手紙(インターネットは開設しているが)でしかない。しかし廃寮推進派は東大出版会を使い、内外評価活動の一環と位置づけて、美しい言葉と単行本で内外に自己主張する。この差が現時点における東京大学の自治における教授会自治と学生(含寮生)自治の差である。前者は権力をもっている。その差である。このような本を作るときに改革批判派の声を反映する自己批判的精神があってもよさそうなのに、それがない今回のような本は廃寮推進派による多数の知の暴力と言わざるをえない、私の率直な感想である。